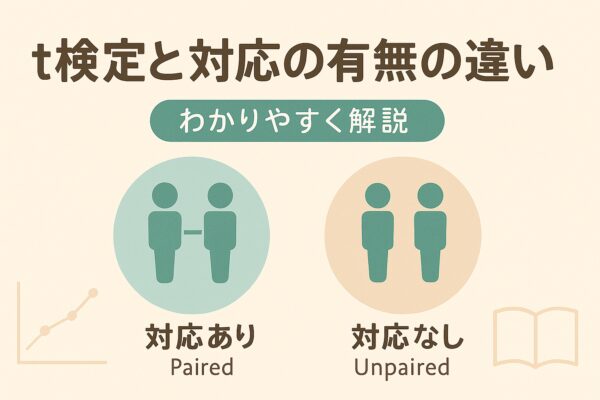

くま先生〜!「t検定」ってよく出てくるけど、なんとなく難しそうで手が出せません…。



大丈夫!t検定は2つの平均を比べるときによく使う手法なんだ。
しかも、覚えるべきは「対応あり」と「対応なし」の2種類だけ。今日はそこをわかりやすく解説していこう!
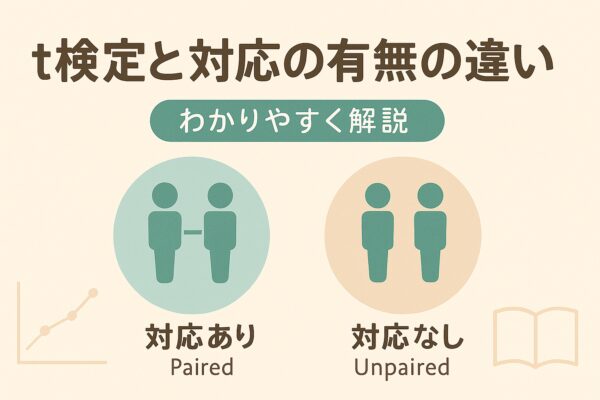
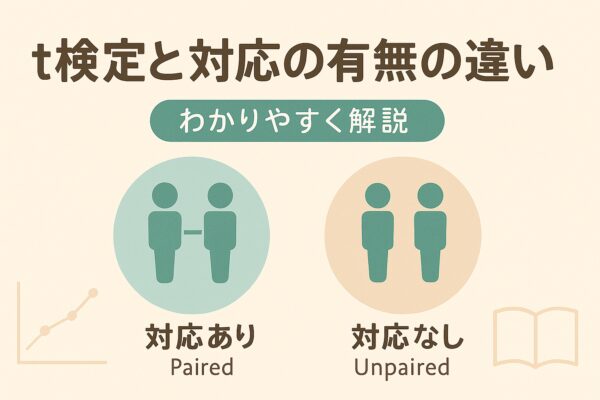
目次
t検定ってどんなときに使うの?



たとえばね──
ダイエット前と後で、体重が変わったか知りたいとき
男性と女性で、平均身長に差があるか知りたいとき
こういうときに使うのが「t検定」なんだ。
なるほど〜!じゃあ、「グループAとBを比べたいとき」に使う検定ってことですね?



対応あり vs 対応なしって何が違うの?
| 種類 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 対応のあるt検定 | 同じ人やモノを2回測る | ダイエット前後の体重、薬の投与前後の血圧 |
| 対応のないt検定 | 別々の人やモノを比べる | 男性と女性の身長、AクラスとBクラスのテスト点数 |
対応ありt検定の例



たとえば10人に薬を飲んでもらって、飲む前と後の血圧を比べたいとき。
これは同じ人を2回測ってるから、「対応あり」だね。
対応なしt検定の例



今度は、薬Aを使った人10人と、薬Bを使った人10人の血圧を比べるとしよう。
この2グループは別の人だから、「対応なし」になるよ。



なるほど…「同じ人が2回測定されたら対応あり」「全然別の人なら対応なし」って覚えればよさそう!



バッチリ!
でも、ちょっとだけ前提条件にも気をつけてね。
対応ありt検定の前提条件
- 差分(2回目−1回目)が正規分布に近いこと
対応なしt検定の前提条件
- 両群とも正規分布に近い
- 等分散性(2群のばらつきが似てる)
※ばらつきが違うときは「Welch(ウェルチ)のt検定」を使うといいよ



なるほど、検定にも“ルール”があるんですね。でもそれって難しそう…。



安心して!最近の統計ソフト(EZR、R、SPSSなど)は、自動で計算してくれるから、
「どんな検定を使うべきか」さえ分かっていれば大丈夫だよ。
まとめ:t検定の使い分けのコツ
- t検定は2つの平均値を比べるときに使う
- 比較する2つが同じ人・同じものなら「対応あり」
- 別々のグループなら「対応なし」
- 前提条件に注意して、適切な検定を選ぼう!
📘 関連記事リンク
- 標本と母集団の違いをやさしく解説
あわせて読みたい

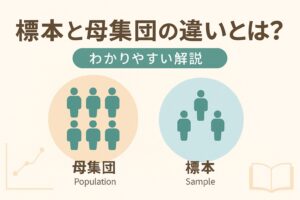
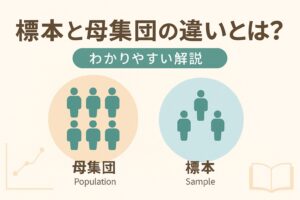
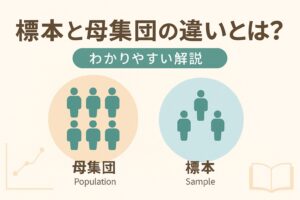
【統計の基本】標本と母集団の違いとは?くま先生と学ぶわかりやすい解説
くま先生~!「標本」と「母集団」ってよく聞くんですけど、いまいち違いがわかりません! いい質問だね。統計を学ぶうえで、「標本」と「母集団」はとても大事なキーワ…
- 代表値の違いとは?平均・中央値・最頻値の比較
あわせて読みたい

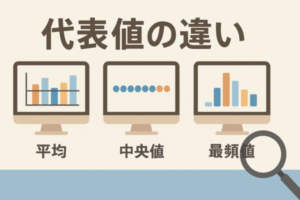
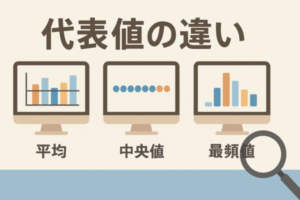
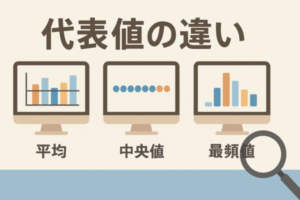
平均値・中央値・最頻値とは?|代表値の違いと使い分けをやさしく解説
はじめに 統計において「データの中心を表す数字」はとても重要です。その代表格が 平均値(へいきんち)・中央値(ちゅうおうち)・最頻値(さいひんち) の3つ。 この…
- 分散と標準偏差ってどう違う?
あわせて読みたい

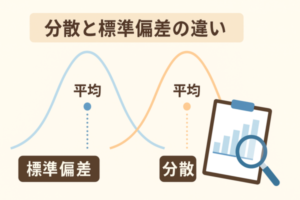
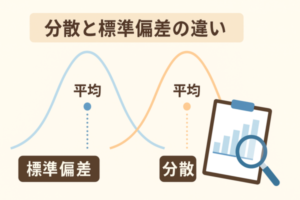
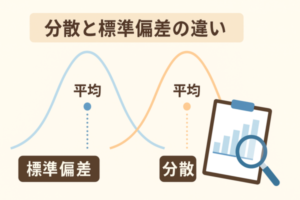
分散と標準偏差の求め方|ばらつきを見る統計の基本をやさしく解説
はじめに 「データの中心」は平均値で見られますが、「データがどれくらいバラバラか?」を表すには、分散と標準偏差が欠かせません。 このページでは、統計の基礎であ…
- 間隔尺度と比例尺度の違いを図で解説
あわせて読みたい




【間隔尺度と比例尺度とは?】定量的データの基本を初心者向けに解説
このページでは、統計初心者の医療者の方に向けて、「定量的データ(間隔尺度・比例尺度)」の違いを、やさしい会話形式で解説します。定量的と聞くと「数字で計算でき…
